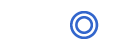第36話:壁の向こう側
2008年 ショートショート
その国の端っこに、大きな"壁"があった。
壁の向こう側を見たものはいない。
より正確には、壁の向こう側を見たものは例外なく、こちらに戻ってこないのだ。だから壁の向こう側がどうなっているのか、誰も知らなかった。
国民の多くは、壁に興味を示さなかった。
そこで世界が終わっている。それだけの話だ。やるべき仕事は多く、そのどれにも壁は関係していない。わざわざ危険を冒してまで、壁に登る必要はなかった。
にもかかわらず、挑戦者はぽつりぽつりと現れた。
跳ねっ返りの若者もいれば、酸いも甘いもかみ分けた老人もいる。壁を登り切る力量を備えたものもいれば、力およばず途中で落ちるものもいる。
共通点があるとすれば……好奇心の強いものばかりだった。
好奇心──。
神はなぜ、そんな感情を私たちに授けたのだろう?
壁の向こう側なんて、どうでもいいのに!
私の兄も壁に挑戦した。さいわい途中で落ちることはなかったが、向こう側に行ったっきり、帰ってこなかった。「さいわい」と言っていいのかどうか。途中で落ちて死んでいたら、こうして気に病むことはなかっただろうに。
そして今、私も壁に登る。
兄がなにを見たのか、気になってしょうがないから。
◎
「また1つ、プログラムが消滅したな」
課長のつぶやきに、私はため息で応えた。
モニタには無数のプログラムの活動が表示されている。ネットから隔離したサーバに無数のプログラムを走らせ、仕事を与える。プログラムたちは役割分担し、経験を共有しながら、より効率的に活動できる環境を模索していく。
私たちは、そのテストをしていたのだ。
"壁"を超えたプログラムはデリートされる。
それは明らかなのに、なぜか足を踏み入れるプログラムが後を絶たない。危険であることを示すため、壁を高くしても効果はなかった。
「"好奇心"を与えると仕事の効率が高まる反面、一定の割合で自滅してしまうのか。難しいな……」
私もコーヒーを飲んで、所見を述べた。
「やっぱり死の恐怖がないから、歯止めが効かないのでしょうね」
「……死の恐怖か。好奇心を与えるのも苦労したのに、ヤレヤレだな。死の恐怖の次は、宗教も必要になるかな?」
課長の冗談はぜんぜん笑えなかった。