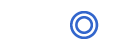第85話:私はここにいる
2010年 ショートショート
宇宙船が燃えている。
起こるはずのない事故が起こってしまった。絶対不変の船体に、赤黒い腐食が広がっていく。基幹部を守るため、まだ乗員が残っているブロックも切り離した。ポロポロ崩れていく宇宙船は、骨だけになった魚のようだ。身も内蔵も捨てて、私たちは助かろうとしていた。
◎
「あなた、風邪を引きますわよ」
そっと肩をさすられ、目が覚めた。
マリアが心配そうに私を見つめている。あぁ、そうか。ここは《故郷》か。昼寝のつもりが、どっぷり日が暮れてしまったようだ。
身体を起こそうとすると、マリアが手を貸してくれた。「老人扱いするな」と言いたいところだが、なにも言わない。ただ心の中で、ありがとうとつぶやく。それがわかるのか、マリアは微笑みで答えた。
杖をついて部屋に入る直前、ふと背後を振り返る。
ゆるやかな丘陵の向こうに、峨々たる山脈がそびえる。まだ青さを残す空に、星が瞬きはじめた。雄大な自然の美しさ。
ここは《故郷》。乗員の大多数がイメージする《故郷》だった。
◎
「総員、ポッドに入れ!」
それが、生身の耳で聞いた最後の声だった。ポッド内でヘッドセットをつけると、アイソレーションジェルが注入される。全身がジェルに包まれると、圧迫感が強い。しかしその息苦しさも一瞬、私の意識は仮想空間に解放された。
宇宙船の被害は大きく、私たちはあまりに遠くにいた。
タンホイザーゲートが使えないため、通常航法で地球に還るしかない。しかし亜光速まで加速しても、地球まで数十年はかかる。大破した宇宙船には、そんな長旅を支える環境は残されていなかった。そこで私たちは、ヴァーチャルポッドに身をゆだねた。
ヴァーチャルポッドは肉体と精神を分離する装置。もともと医療用だが、改造して生命維持装置にした。肉体はジェルから栄養補給し、精神は中央サーバに接続され、仮想空間で共同生活するわけだ。
実際はポッドごとに格納されているのに、精神は互いに触れあえる。
実際はジェルで固定されているのに、精神は草原を駆け回っている。
実際は点滴で生きているのに、精神はごちそうを食べた気になる。
実際は秒速30万キロメートルで飛行しているのに、精神は故郷に留まっている。
宇宙船の航行はコンピュータが制御している。
私たちの仕事は、正気を保つことだった。
◎
「あなた......」
マリアに言われ、われに返る。
食事の最中だった。今夜のメニューは鹿肉のソテーにシチュー、それにライ麦パン。天上の美味、と言いたいところだが、よくわからない。マリアの味付けに慣れてしまったせいか、年老いて味覚が衰えたせいか。いや、衰えたのは脳そのものか。
「夢を、見ていたんだ」
「夢?」
「あぁ、事故当時の夢を......」
「......」
重い話題に、マリアは目を伏せた。
マリアと暮らしはじめて、かれこれ30年か。仲間はみんな、死んでしまった。自殺した者、発狂した者、そのどちらともつかない者......。果てしない旅に、精神が堪えられなかった。
だが私は生き延びた。マリアがいてくれたから。
以前のマリアは共有財産だったが、今は私だけのもの。私だけを見てくれる。マリアは、この宇宙船のマザーコンピュータだった。
「そうだな。寝るとしよう」
マリアに支えられ、年老いた身体をベッドに横たえる。
「次に目覚めたら、地球かな?」
「いえ、地球には、まだ少し......」
マリアはあいまいに答える。
実際、地球までの距離がどれほどあって、私の寿命が足りるかどうかは、あまり興味がなかった。
それより気がかりなのは、新たな事故だ。たとえば、どこぞのエイリアンが船をつかまえて、ポッドから私の身体を引っ張り出したら?
(それで死ぬのは怖くない。怖いのは、目を開けることだ)
マリアは聡明な女性なので、私を不安にさせるようなことは言わない。仮に今、いま私の生命維持に危険が迫っていても、決して悟らせないだろう。そう、設定してある。
「このまま死んでしまいたいよ」
私のつぶやきに、マリアは微笑みで答えた。
(1,613文字)
今回は1,000文字にまとめきれなかった。削っちゃうと、あまりに殺風景だったから。ずっと1,000文字でショートショートを書いてきたが、そろそろ「枠」を打ち破ってもいいかもしれない。