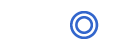缶切りが見当たらなくて、思ったこと
2016年 科技
スパムの缶詰を開けようとしたら、タブが切れてしまった。
仕方ないから缶切りを使おうとしたら、見当たらない。ないわけないので探すと、引き出しのずっと奥に押しやられていた。そういや、缶切り使うのも久しぶりだ。
イージーオープンエンド
道具を使わず開口できる缶蓋を「イージーオープンエンド」と呼ぶ。
缶ジュースのプルトップも含まれる。言われてみれば缶ジュースも缶詰の一種だった。缶ジュースの飲みくちのように、部分だけ開くものをパーシャルオープンエンド、ツナ缶のように缶蓋全体が開くものをフルオープンエンドと呼ぶ。日本では「パッ缶」の愛称で親しまれている。
私の記憶では、フルオープンエンドのはじまりはツナ缶だった。やがて魚介類、豆、果実、肉、惣菜などに広まっていった。今じゃ缶切りがないと開けられない缶詰を探す方が難しい。ひょっとしたら近ごろの子どもは、缶切りを使った経験がないかもしれない。
電動缶切り機
子どものころ、親父が電動缶切り機を買ってきた。いま思うと、珍しいアイテムを買ってしまうのは、親父の悪いクセだった。しかしまぁ、電動缶切り機はおもしろかった。磁石で蓋をくっつけ、モーターで回しながら切ると、きれいに開缶できる。いまはフルオープンエンドで珍しくもないが、当時、きれいな切り口は驚きだった。
たくさん缶切りして怒られたっけ。そうそう、缶ぽっくりとか、太陽光でお湯を作る装置とか作ったなぁ。空き缶は子どもにとって魅力的な加工素材だった。
電動缶切りは進化して、いまも売られていた。缶詰も鉄製と限らなくなったから、磁石で吸着するタイプはないようだ。ふと、電動鉛筆削りを思い出す。鉛筆を削ることが減っても、あるいは減ったからこそ、電動鉛筆削りは便利かもしれない。いまも小学校とかにあるのかな?
久しぶりに缶切りを使ったので、あれこれ調べてみたが、けっこう技術の変遷があった。世の中、便利になっていくねぇ。