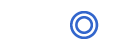【ゆっくり文庫】ヘルマン・ヘッセ「少年の日の思い出」 Jugendgedenken (1931) by Hermann Hesse
2014年 ゆっくり文庫 ドイツ ドラマ
021 少年たちがつぶしてしまったもの──
子どものころ、ぼくは蝶集めに夢中だった。エーミールはぼくの獲物に難癖をつけたので、疎遠になった。ところがエーミールが珍しい蝶の羽化に成功したと聞き、見てみたくなった。
原作について
国語の教科書に60年以上も掲載され、子どもたちの心を苛んできた作品。
しかしどうも引っかかる。主人公がそれほどエーミールを嫌っていたなら、展翅技術を高く評価したり、青いコムラサキを見せに行くだろうか? 主人公の偏見が強すぎて、エーミールの実像が見えない。
おそらく主人公とエーミールは親友同士だったのだろう。しかし決裂したことで、主人公は仲がよかったころの思い出まで歪めてしまった。主人公がコレクションだけでなく、エーミールとの思い出までつぶしてしまったのだ。
本作は、大人になった「私」が「ぼく」の回想を聞くという構成になっている。これは、「ぼく」が信頼できない語り手であり、本当の主人公は「私」であるという暗示ではなかろうか? また妹にしか見せていなかったコレクションをエーミールが知っていたことも、謎解きのヒントに思える。
ヘッセの意図はわからないが、そう考えると納得できた。
傷つきやすい主人公、傷つけやすいエーミール
エーミールに、「主人公を強く意識している」「気持ちをうまく伝えられない」という属性を加えてみた。ストーリーは同じでも、受ける印象はだいぶ変わるだろう。
エーミール視点の過去や、ふたりの再会シーンも考えたけど、原作から乖離しすぎるので割愛した。作ったシーンをカットするのは苦しかったけど、やむなし。あれこれ詰め込まず、ただ、やり直すチャンスがあることだけ強調しておこう。
作品論と作家論、妄想論
物語を読み解く手法として、書いてあることのみ斟酌する「作品論」と、作家の人格や背景を考慮する「作家論」がある。作品論に立てば、大人同士の回想は不要だ。作家論に立てば、エーミールという名前(ヘッセのペンネーム)や母親に諭されるシーン(ヘッセの母との関係)が意味をもつが、それだけじゃ足りない。
私はいつも、自分が読みたいように読んでいる。作家の意図も、書いてある筋書きも無視して、感動したいように感動する。いわば「妄想論」だ。
国語の点数はもらえないが、【ゆっくり文庫】なら許容されるだろう。たぶん。
動画制作について
私は昆虫が苦手なので、チョウチョの写真は載せなかった。青いコムラサキはどう青いのか? クジャクヤママユはどんな斑点をもっているか? Wikipediaで確認したけど、無ー理ー。ぞわぞわする。【ゆっくり文庫】では、チョウチョを「美しいものの象徴」として描き、実像は伏せることにした。容赦されたし。
ちなみにドイツ語の「Schmetterling」は蝶と蛾の総称(鱗翅類)である。主人公やエーミールは、蝶だけでなく蛾も収集している。正確を期すなら「蝶と蛾」と書くべきだが、「チョウチョ」と呼ぶことにした。
現在(大人)を上段に、過去(少年)を下段に配置して、回想していることを強調する画面構成にした。少年も大人も同じキャラクター(れいむ)だけど、メガネと表情で差を演出したのだが、どうだろう?
原作では回想で終わってしまうが、やはり現在→過去→現在と場面を戻すことにした。画面構成を工夫したことで、過去と現在の連続性が演出できたと思う。
本作では表情をいくつか追加した。きつねゆっくりのパーツを切り貼りして、足りないところはマウスで描画した。たいへんだった。
作った表情は今後も使えるから、少しずつ表現力が高まっていくだろう。作ったパーツは配布した方がいいかな?
 マジ泣き (口) |
 沈み (目) |
 沈み&涙 (目) |
|
 やつれ (顔) |
 ジト目の流し (目) |
 ジト目の見下し (目) |
たくさん考えたプロットをどこまで描くべきか。
どこまで原作から離れていいのか。
悩んでも仕方ないので公開する。反響があれば、エーミール視点も描いてみたい。
【ゆっくり文庫】少年の日の思い出:エーミール視点
結局、エーミール視点も作ることにした。プロットは本編を作る前から固まっていたし、ほとんどのシーンを使いまわせたから、あっという間に完成した。すると「こんなものを公開していいのか?」「まったく余計なことを得意になって語っているのではないか?」と悩むようになった。しかしまぁ、文学を読んだ時に感じた妄想を垂れ流すことが【ゆっくり文庫】シリーズの目的なので、えいやと割りきった。馬鹿にされても、失うものはない。
当初は、エーミール視点も含めて1本の動画にするつもりだった。しかしこうして分けたのは正解だな。振り返れば、「黒猫」や「ボヘミアの醜聞」も二部構成にすべきだった。とはいえ、本編と妄想は不可分だから、こうして分割できる作品は多くないだろう。
内容について少し。
エーミール視点は、本編の少し前の出来事である。私(レミリア)は、エーミール(ゆかり)が語る「彼」=ぼく(れいむ)と考え、招待した。ぼく(れいむ)の話を聞きながら、思い出が歪んでいるに気づいた私(レミリア)は、細心の注意を払ってエーミールとの再会を提案した。けっこう大変な役どころだ。
再会したふたりはドラマティックな会話もなく仲直りできただろう。もちろん、少年時代のような仲良しになれるわけじゃないが、その必要もない。わだかまりと向き合い、自分や相手を悪く思うことから解放されればいいのだから。
「一房の葡萄」を作ったとき、主人公のいない教室で先生が話したこととして「少年の日の思い出」を思いついた。さらに先生=ぼくの妹と閃いた時点で、動画を作ることが決まった。シーンとしては最後だが、ここが出発点だった。ほかの作品と関連付けるのも反則っぽいが、妄想なので許してもらいたい。
演出メモ
- エーミールは「彼」(れいむ)を悪く言いたくないので、名前や詳細を伏せて話した。また私(レミリア)が興味ない専門用語も避けている。なんだかんだでエーミールは気配りできる。
- ぼく(れいむ)視点で単色だった背景が写真になったのは、より正しい記憶だから。本当のエーミールはよく笑うし、ぼく(れいむ)は仏頂面だった。
- エーミールにどのように謝罪したか、原作に具体的な記述はない。しかし「盗もうとした」とは言わなかっただろう。エーミール視点では、「盗もうとした」と言えば誤解されなかった。まぁ、ちゃんと言っても聞き取れなかった可能性はある。口にしただけで気持ちが伝わるなら苦労しない。
- この事件を経て、エーミールは悪党として振る舞うようになる。少年時代の早すぎる終わりだ。その印象が、ぼく(れいむ)の思い出を歪めている。現在のエーミールが思い出に登場するのはそのせい。
- エーミールは自分を悪党と思っているので、子どもと接するとき臆病になる。
- 本編において私(レミリア)が、「でもね、私たちは生きている」と言ったのは、父親と死別したことに起因している。やり直すなら生きているうちで、人生は思うほど長くない。私も、父親と死別したことでいろいろ気づいた。
- エーミールを擁護しているが、潔白というわけじゃない。エーミールは、ぼく(れいむ)に嫉妬したことを隠したいから、誤解したことを告白できなかった。
- ぼく(れいむ)に非があることを強調するため、「仏頂面で言葉が足りない」という属性を加えた。エンドカードのふたりが真実である。
- 「双方と話せる人がいなかったことが悔やまれる。」とは、「一房の葡萄」の先生(まりさ)がいないことの暗示。
- エンドカードつけたら、最終回っぽくなった。
- なんだかんだで、悪いのはきめぇ丸。
以上が、私が感じた「少年の日の思い出」である。
頭の中にあったものを出力できて、私は満足だ。