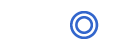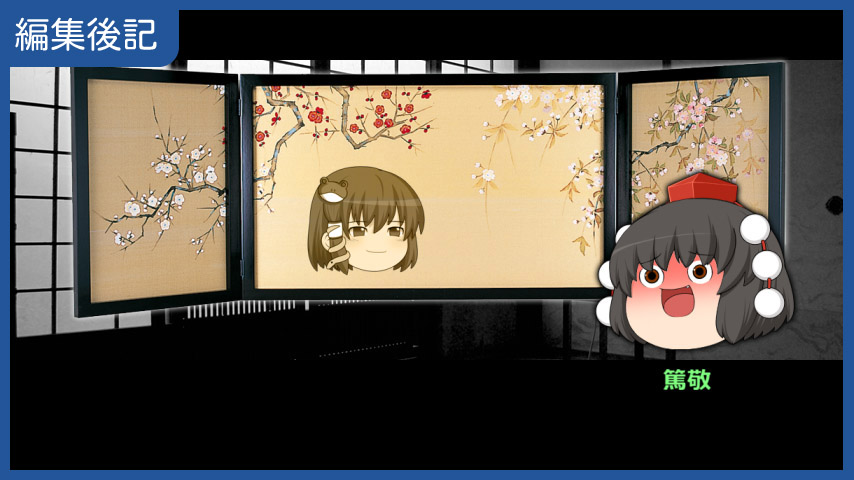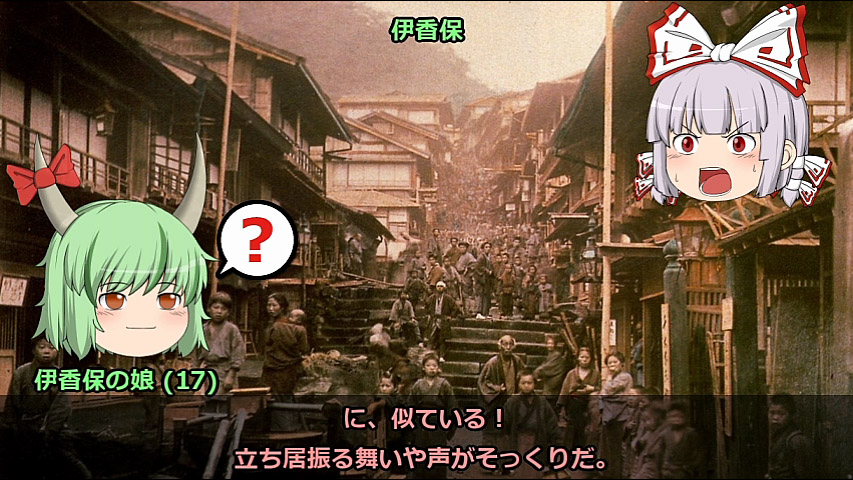【ゆっくり文庫】小泉八雲「葬られた秘密」 A Dead Secret (1904) by Lafcadio Hearn
2016年 ゆっくり文庫 ファンタジー 小泉八雲 日本の民話 日本文学 民話・童話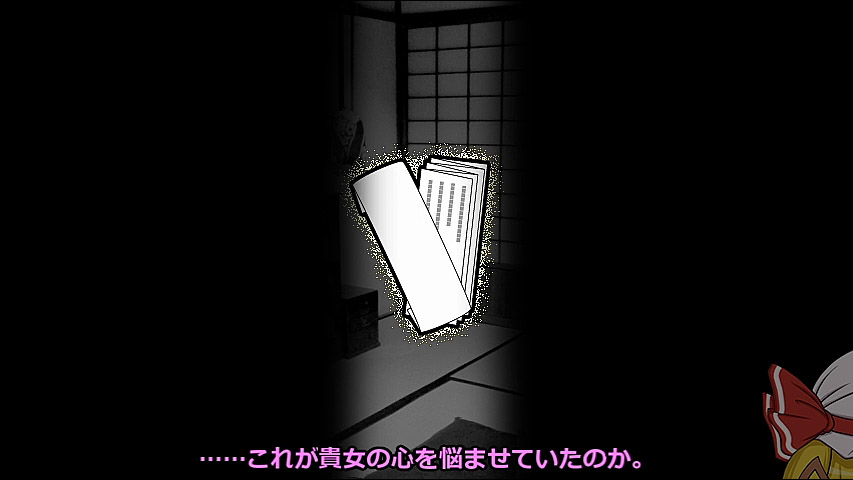
049 お母さんの秘密──
お園は美しく怜悧な娘であったが、流行り病のため亡くなった。ところが葬儀の後、たびたびお園の霊が現れるようになる。家族は戸惑い、高名な僧侶に相談した。
原作について

小泉八雲
(1850-1904)
幽霊が出たのに退治せず、秘密も明かされない──。
はじめて読んだときは戸惑ったが、「もし秘密を暴いていたら?」を想像すると納得できた。
死者の秘密を暴くことは、死体を辱める行為に等しい。ささいな秘密なら嘲笑し、重大な秘密なら憤慨し、死者への敬意は失われ、嫌悪感だけが残る。箪笥を穢れたものとして焼却し、部屋を封じても、家族は疑心暗鬼に囚われる。自分も死ねば、秘密を暴かれるのだ。家族さえ警戒せねばならぬとしたら、それこそ恐怖の家だろう。
死者への配慮は、やがて自分に還ってくる。
死者を辱めたものに、どうして平穏が訪れるだろう?
死者の気持ちに寄り添うこと──それが「供養」なのだ。
- [青空文庫] 『葬られたる秘密』戸川 明三訳:新字新仮名
- [原文:英語] The Project Gutenberg E-text of KWAIDAN: Stories and Studies of Strange Things, by Lafcadio Hearn
- [解説] 葬られた秘密 - Wikipedia
和尚が守ったもの
幽霊を退治するか、秘密を伏せておくか? 家族に議論させなかった和尚の知恵に感服する。もちろん箪笥の中は空っぽで、「手紙を焼いた」というのは和尚のウソかもしれないが、家族が得たものは変わらない。
和尚は幽霊を退治するためではなく、恐怖を祓うため訪れたのだ。
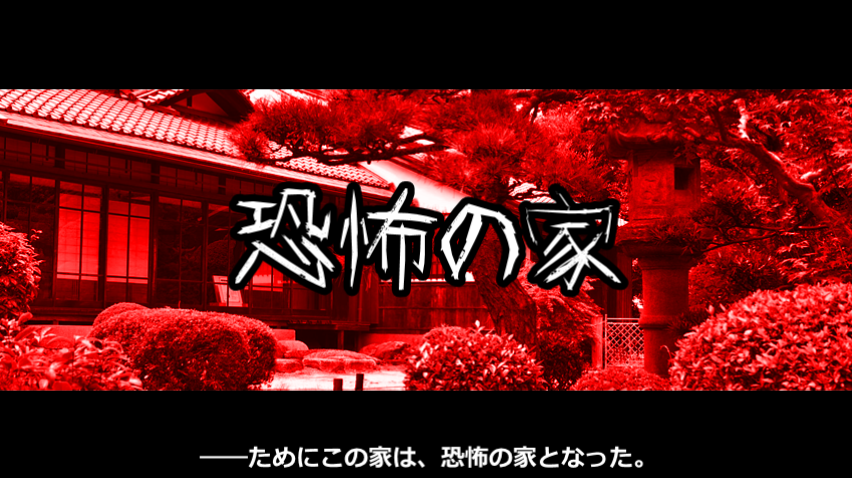
※恐怖の家
お母さんの秘密
さりとて秘密が気になるから、妄想推理してみよう。
投函されなかった恋文や、「葉桜と魔笛」のような創作文、恋愛以外の機密文書という可能性もあるが、男性から愛の告白をされたものと仮定する。相手が身分ある方で、迷惑を掛けたくないなら、処分するはず。急死のため処分できなかった可能性もあるが、むしろ死の瞬間まで忘れていたのではなかろうか?
お園は素敵な男性から素敵な恋文をもらって、うれしく思った。それは乙女の思い出となり、箪笥の奥に隠された。結婚後は幸福な日々の中で忘れ去られていたが、今際の際に、ふと思い出した。
(あんな手紙が見つかったら、主人が傷つく! 家族が困惑する!)
家族に知られず手紙を処分する方法は...あったかもしれないが...
(手紙を焼いたら、あれは、なかったことになるの?)
と迷ってしまった。
結局、お園は手紙が気になって成仏できず、箪笥の前に立ってしまうのだった。
「だれも知らない秘密」なんて、存在しないも同然だ。和尚が口をつぐんだことで、秘密は秘密でいられた。秘密がある女として死ねたことは、お園の魂を慰めたことだろう。そして家族も、秘密を葬ってやれたことを誇りに思っているだろう。
翻案について
八雲の筆致はあまりに淡白だから、家族の焦燥や安堵を演出したい。
下記は発想の変遷。
- 第一稿:成人したお園の息子が回想する
ぼくのお母さんには、秘密がある。という書き出してはじまる。なかなか鮮烈だったが、「女の秘密」が強調されすぎたため没に。
- 第二稿:息子をお母さんの代弁者に
死を理解しない息子は、お母さんを異物のように扱う家族に戸惑う。和尚も警戒するが、結果に満足する。成り行きを変えるような行動はしないが、いいアクセントになった。
- 第三稿:成人した息子の妻子を追加
稲村屋源助(ゆかり)、婿(こーりん)、孫(ふらん)、ひ孫(ちぇん)という4世代が住む「家」がクローズアップされた。

※死んでもお母さんはお母さんでしょ?
おまけ:八雲とセツの会話シーン
ラフカディオ・ハーンは日本の「盆踊り」をこよなく愛した。盆踊りとは、死者の霊を招いて、いっしょに踊る行事である。これは西洋(キリスト教圏)では考えられないことだった。
キリスト教の死者は天国(異次元)に召され、神によって祝福される。それは永遠に約束されたことだ。ゆえに幽霊は基本的に邪悪であり、異物であり、排除すべきものだ。
日本では、生者が死者を供養する。その営みを絶やさぬ努力が求められる。死者は供養してくれる子孫の繁栄を願う。生者と死者の共存関係ができている。
日本の死者は神となり、自然の一部となって、海や山、塚、あるいは家に棲む。生者はつねに死者の視線を感じているが、「監視されている」とは思わず、「先祖の霊に恥じない自分でありたい」と自分を律する。ゆえに日本人は幽霊を排除せず、その思いに耳を傾け、寄り添おうとする。
ハーンはどれほど驚いただろう。
といった話を会話で表現すると、本編以上に長くなるため、カットした。つらいけど、正しい判断だったと思いたい。でも、つらい。

※八雲とセツの会話シーンはカット
動画制作について
お園役は当初、早苗だった。美しく、賢く、秘密のある女のイメージにぴったりだったが、「武家に婿入りした八雲」を暗示するため、霖之助と魔理沙の組み合わせになった。動画を見れば「これしかない」と思うかもしれないが、制作中はゴールが見えない。早苗から魔理沙に変えたときは違和感が強かったが、やがて慣れた。不思議なものだ。

※早苗も悪くなかった
家族の呼び名
日本人は家族の呼び名を、もっとも幼い者の視点に合わせる。夫婦に子が生まれれば、子から見て「お父さん/お母さん」になり、孫が生まれれば、孫から見て「おじいちゃん/おばあちゃん」になる。ひとりっ子なら名前で呼ばれるが、第二子が生まれれば「お兄ちゃん/お姉ちゃん」だ。
もっとも幼い者が混乱しないように、家族全員が協力する風習は素晴らしいので、動画に組み入れてみた。

※家族の呼び名はもっとも幼い者の視点で変わる

※そして、受け継がれていく
隙間から覗き見
ふと思いついて、和尚とお園が会話するシーンは「隙間から覗き見する」よう演出した。会話シーンを作ってから隙間フィルターをかぶせたので、塗りつぶされた部分にも表情がついている。
「だれが覗き見したか?」が気になったので、息子(ふらん)の後ろ姿が追加された。もろもろ作りながら思いついてる。

※塗りつぶされた部分にも表情がついている
右か左か
【ゆっくり文庫】では、たいてい右にいるのが主人公だ。厳密なルールではなく、例外も多いし、なぜそのように演出するのか、自分でもわかってない。
今回の動画で言えば、家族のシーンは息子が右にいる。家族がいないシーンは和尚が右にいる。家族と和尚がいるシーンでは左右が混在していたが、違和感があったので家族を右に揃えた。
いつも同じ配置だと単調になるが、今回はこれで安定したと思う。なぜ違和感があって、なぜ安定するのか、論理的な説明はできない。

※主人公は右に
背景の明るさ
細かいことだし、気づいている人もいないだろうが、問題発生後は背景が暗くなっている。登場人物の気持ちが沈むと、背景も暗くなるのだ。私は動画編集の技術が乏しいので、こうした明るさや彩度をいじる演出が多い。

※気持ちが沈むと、背景が暗くなる
レミリア改修
きつねゆっくりは400ピクセル幅に描画されているが、レミリアとフランは翼があるため440ピクセルになっており、見た目の中心が37ピクセル左にずれている。
画角の中心とオブジェクトの中心が異なるため、字幕がズレたり、反転させたときのブレが大きくなる。今回、レミリアとフランの全画像をバッチ処理して、ほかのキャラクターと軸線を揃えた。
まぁ、制作サイドの都合だが、そういう作業をしたことを記録しておく。
それとレミリアをやや小顔にして、前髪にハネを加えている。細かく手が入っている。

※ゆっくり文庫版レミリア、地味に変えている
雑記
「雪おんな」で予告したので、次は「お貞のはなし」になると思っていただろうが、本作を先にした。意表を突くためだ。
ちなみに本作が完成したのは昨年8月。正月スペシャルで4本連続公開するつもりだったが、間隔をあけた。長く寝かされた動画を公開できるのはうれしいが、ストックがなくなるのは寂しい気もする。
そういえば新年の挨拶動画を作らないとなぁー。