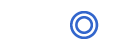無実はさいなむ / アガサ・クリスティーのミス・マープル (S3E2) Agatha Christie's Marple: Ordeal by Innocence
2007年 海外ドラマ 4ツ星 家族 探偵 @アガサ・クリスティ「グェンダはここで家族を見つけたんです」
あらすじ
グェンダは、富豪のリオ・アーガイルの秘書を勤めていた。リオと妻レイチェルの間に子供はなく、夫妻は6人の養子を迎え入れていた。その中の1人ジャッコはいつも金の無心に来ていた。レイチェルは気性が荒く、夫のリオにさえ役立たず呼ばわりしていた。
(c) ITV PLC (c) ITV UK / Film Afrika Worldwide
ノン・マープルより。マープルさんは秘書グェンダの恩師という設定で、結婚式に招待される。グェンダがマープルさんを尊敬していることがわかるので、とても自然な導入部になっている。結婚式が流れ、グェンダが死んでも滞在するのは無理があるが、展開が早いので気にならない。
グェンダはもっとマープルさんをたよるべきだった。新たな家族を得るため、独力で解決しようとしたのだろうか。そんなグェンダを、アーガイル家の人々は拒絶した。許せないことだ。マープルさんがグェンダの無念を伝えるシーンが胸に響く。
犯人は家族のために罪を認めたが、家族は犯人の手を拒絶した。当たり前といえば当たり前だが、アーガイル家の人々の不誠実さが目立つ。彼らは互いを信用せず、他者の犠牲を顧みない。疑惑は晴れたが、守るべき家族の絆は残っていなかった。なんという皮肉だろう。
キャルガリーが脳天気な学者バカとして描いたのは正解だ。おかげで証言を疑わずに済んだし、家族でない者の視点も得られた。『ドーバー海峡殺人事件』(1984)のキャルガリー(ドナルド・サザーランド)は悪人っぽい雰囲気だったのと対照的だ。しかし脳天気すぎて中盤以降は居場所がなかった。まぁ、安易に家人と恋に落ちても困るか。
レイチェルはなぜ子どもにこだわったのだろう? 資産を継がせることに執着していたのか? もしレイチェルに資産がなければ、ここまで子どもたちに嫌われることもなかったかもしれない。
マープルさんさんはヘヤピンで金庫を開けてしまった。どういう人生を歩めばそんなスキルが身につくのか。「甥がよく鍵をなくすから」などという説明じゃ納得できない。まぁ、このくらいスーパーマンでもいいか。
| アガサ・クリスティ | |
|---|---|
| ポワロ | |
 |
デビット・スーシェ (David Suchet) |
 |
ピーター・ユスティノフ (Peter Ustinov) |
 |
声:里見浩太朗
|
| ミス・マープル | |
 |
マーガレット・ラザフォード |
 |
アンジェラ・ランズベリー |
 |
ヘレン・ヘイズ |
 |
ジョーン・ヒクソン |
 |
ジェラルディン・マクイーワン |
 |
ジュリア・マッケンジー |
 |
声:八千草薫
|
 |
ゆっくり文庫 |
| 奥さまは名探偵 | |
| ほか | |
| 検察側の証人 | |
| そして誰もいなくなった | |
| ほか | |